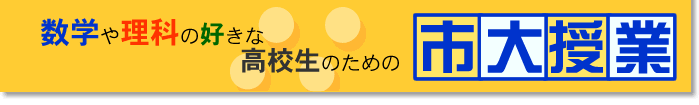|
|
| 数学や理科の好きな高校生や予備校生の皆さんに、数学や理科にさらに興味を持ってもらえるように企画した「高校生のための市大授業」です。大学の授業や大学の教室・実験室がどんなものなのか、進学を希望する大学の中を知っていただきたく、本学杉本キャンパスで行います。2004年、2005年、2006年に引き続き7回目の市大授業です。日程は4月30日(月・祝日)です。高校や予備校からのFAXでの一括申込ばかりでなく、個人的申込方法(葉書や電子メール)も採用します。前半(吉田、村田、小宮)と後半(橋本、三宅、前島)の2つの授業を受けることもできます。詳細は大阪市立大学理学部ホームページ(http://www.sci.osaka-
cu.ac.jp/)に平成19年3月から掲載します。定員を超えた場合には教室を変更してできるかぎり受講可能とします。受講不可能のときのみ、4月25日(水)に連絡します。 2007年4月30日(月・祝日) <終了しました> |
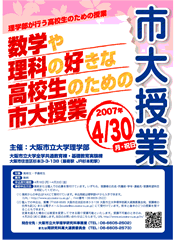 |
| ◇前半:午後1時00分〜午後2時30分 | ||||||||||
| 微分から偏微分へ 〜極値問題を中心に〜 | ||||||||||
 |
数学科 講師 吉田雅通 (定員100名、講義) 「微分」の身近な一例としては「速さ(速度)」があります。授業では最初に、いくつかの例をあげながら、微分について説明していきます。微分で何が分かるの?と思う人もいるかもしれません。実際、微分は様々なことを教えます。正確には、微分は「関数の微分」と言います。関数は y=f(x) という形で教科書に出てくるでしょう;y=f(x) を詳しくは1変数関数と呼びます。微分の一つの応用問題として関数の最大値や最小値を求めること、より一般に「関数の極値問題」があります。そこで今度は、z=f(x, y) という形 (2変数関数)、なじみがない形と思いますが1変数の微分法を推進するつもりで、いくつかの例を通じて「偏微分」の考え方と応用を紹介していく予定です。 |
|||||||||
|
||||||||||
| 極限世界の物質 | ||||||||||
 |
物質科学科 教授 村田惠三 (定員100名、講義) 人類の暮す地球は、温度・圧力、そして磁場、とっても優しい宇宙のゆりかご。それを変えたらどうなるか?それを変えるは我々自身。物質世界は千変万化。炭はダイヤに、絶縁物には電気が通り、超伝導すら手にしてしまう。暖めなくてもゆで卵、薬使わず殺菌実現、それも可能だ。そんな環境、どうして作る?どうして測る?どこまでいける?極めてみよう、物との付き合い。 |
|||||||||
|
||||||||||
| 発生のダイナミクスと遺伝子の働き:発生生物学への招待 | ||||||||||
 |
生物学科 助教授 小宮 透 (定員100名、講義) 精子と卵が合体(受精)し、その結果として卵割という細胞分裂を繰り返して動物のからだができ上がっていきます。この過程を「発生」といいます。「我々の筋肉や精子や卵細胞はどのように作られていくのか?」、このような疑問に対し、仮説を立てて実証する学問が「発生生物学」です。 20世紀末から今世紀にかけ「遺伝子」に関する情報が膨大なものになりつつあります。特に細菌やハエや線虫などの生物だけでなく人やマウスのゲノムの配列が決定されました。そしてこの情報を基盤として発生生物学や医学の研究が急速に進歩しています。 この講義では上記の遺伝子に関する学問(分子生物学)の最近の進歩と発生の現象を遺伝子のことばとして語る「現代の発生生物学」についてちょっとだけ紹介します。 |
|||||||||
|
||||||||||
◇後半:午後3時00分〜午後4時30分 |
||||||||||
| “光合成”をこの手に! | ||||||||||
 |
物理学科 教授 橋本秀樹 (定員100名、講義) 光合成系は生命が38億年と言う気の遠くなるような歳月をかけ、自然選択と言う過酷な条件のもとで様々な試行錯誤を繰り返した結果創成された、地球上における最高の光エネルギー変換機関です。クロロフィル(葉緑素)やカロテノイド(カロチン色素)と言った特定の光合成色素が、蛋白質に支えられてナノメートルスケールの空間に規則正しく配列した、見た目にも美しい色素蛋白複合体構造(下図参照)がその機能発現に密接に関係しています。したがって、生体による光操作と言う観点から眺めた場合、この色素蛋白複合体は生命維持の目的のために最適化されたバイオナノデバイスと呼ぶことが提案されます。実際に光合成反応では、捕らえた光エネルギーを使って電子を発生する、つまり太陽光発電が行われています。 市大授業では、自然が創造した太陽電池の構造と機能、さらには人為的に色素構造を改変した人工のバイオ太陽電池の創成について講師の研究成果も交えながら話題提供したいと思います。工学的応用と言う立場から、光合成研究に関する最新の知見及びテクノロジーを用いて複雑な光合成反応がどのように或いはどの程度制御できるのかについて共に考える機会を提供したいと考えています。 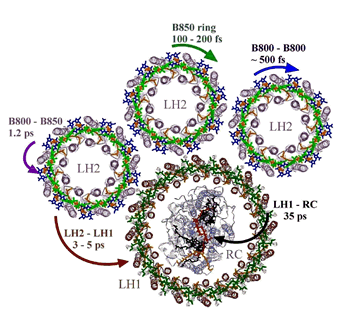 最新のテクノロジーが明らかにした光合成系の構造 |
|||||||||
|
||||||||||
| 分子のダイナミクス 〜化学平衡を征するものはナノ世界を征する〜 | ||||||||||
 |
化学科 助教授 三宅弘之 (定員100名、講義) 我々『ヒト』も含めて、生命が宿る生き物の体内では、様々な化学反応を巧みに操り、次世代へと命を繋いでいます。必要なときに、遺伝などの必要な情報を伝達するため、その"時"を察知し、適切な反応を起こさなければいけません。どうやって状況を知り、反応が始まるのでしょうか?『化学平衡』の連鎖が1つの答えといえます。この授業では、分子の世界を支配する『化学平衡』がどういうものかを解説(復習?)し、その現象を利用した身の回りにあるセンサーや、さらには人工ナノ分子マシーン構築への挑戦などについて紹介します。 |
|||||||||
|
||||||||||
| 地層形成のメカニズム 〜水流がつくる砂のさざなみ〜 | ||||||||||
 |
地球学科 教授 前島 渉 (定員20名、実習) 地層は水の流れによって運ばれた砂や泥などが層状に積み重なってできます。水の流れによって水底の砂が動かされると、砂は水底に規則的な波形の起伏をつくりながら動いていきます。砂のさざなみがあらわれるのです。起伏をならして砂をたいらにしてやっても、水の流れがあると再び波形の起伏ができてしまいます。流れの速さや深さ、砂つぶの大きさなどによって、波形の起伏の形や大きさがちがってきます。高さが1cmに満たないごく小さいものから1m程度のもの、さらには数mを超えるものも知られています。川の流れであっても、海の潮流であっても、とにかく水の流れがあると砂は規則的な波形の起伏をつくって動いていくのです。地層にはこのような波形の起伏やその痕跡がしばしば残されており、地層ができた時の水の流れの状態を知る手がかりとなります。 この授業では、全長約13mの実験水路を用いて水の流れによって砂を動かし、規則的な波形の起伏をつくってみます。自然の川などとちがって規模の大きなものはできませんが、それでもきれいな砂のさざなみを見ることができます。流れの速さを段階的に変えて、水の流れ方と砂の動き方、波形の起伏のでき方、その形や大きさの変化などを観察します。 |
|||||||||
|
||||||||||