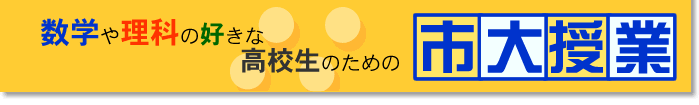|
|
数学や理科の好きな高校生や予備校生の皆さんに、数学や理科にさらに興味を持ってもらえるように企画した「高校生のための市大授業」です。大学の授業や大学の教室・実験室がどんなものなのか、進学を希望する大学の中を知っていただきたく、本学杉本キャンパスで行います。平成16年春から始まった市大授業も今回で11回目となります。日程は4月29日(水)です。申込は理学部ホームページ(http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/koudai/koudai.html)で受け付けます。ホームページから申し込むことができない場合は、FAXによる申込も可能です(FAX番号:06-6605-2522)。前半(午後1時から)と後半(午後3時から)の二つの授業を申し込む事ができます。定員を大幅に超える申込があった場合は、受講をお断りする場合があります。受講不可能な場合に限り4月24日(金)までにご連絡します。 |
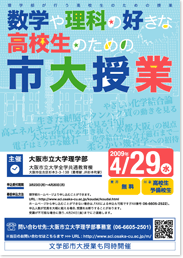 |
| ◇前半:午後1時00分〜午後2時30分 | |||||||||
柔らかい幾何学への招待 |
|||||||||
 |
数学科 教授 枡田幹也(定員100名、講義) 20世紀に目覚ましい発展を遂げた数学に,トポロジーという学問があります.数学には(残念ながら)ノーベル賞はありませんが,代わりに(40歳までの研究者を対象とした)フィールズ賞があり,20世紀におけるフィールズ賞受賞者の多くがトポロジーに関連した研究をしていることを見ると,20世紀の数学界はトポロジーの時代だったと言えるかも知れません.高校までに習うユークリッド幾何学は図形の形を変えることを許さない硬い幾何学ですが,トポロジーは「ゴム風船の幾何学」とよばれる柔らかい幾何学です.この授業では,トポロジーの考え方,意外な応用を話します.柔らかい幾何学を通して頭を柔らかくしてみませんか.
|
||||||||
| 電子はミクロな磁石 ー化学結合から分子磁石までー | |||||||||
 |
化学科 教授 手木芳男(定員100名、講義) 電子は、マイナスの電荷を帯び“自転(スピン)している”ためミクロな磁石としての性質を持っています。この電子の自転(スピン)の向きは、物質が関係する色々な化学現象、物理現象に本質的に重要な役割を担っています。皆さんが高校で聞いた事のあるものとしては化学結合や化学反応、元素の周期律、物質の磁石としての性質(磁性)、発光現象(りん光)などに関係しています。この講義では、化学結合と元素の周期律から始まって、分子中の電子の状態や、最近の研究領域である有機物の分子磁石までを電子のスピンというものに焦点を絞って講義します。
|
||||||||
| 生きた細胞でタンパク質の動きを見る | |||||||||
 |
生物学科 准教授 中村太郎(定員100名、講義) 下村脩さんがノーベル化学賞を受賞されたことは記憶に新しいと思います。下村さんが発見された緑色蛍光タンパク質 (GFP)は、現在の生物学とくに細胞を見る分野ではなくてはならない道具となっています。本授業ではGFPはなぜ現在の生物学になくてはならないのか、その発見の歴史から最新技術を紹介します。さらにGFPやその他の蛍光タンパク質を使った例を私の研究も含めて紹介します。
|
||||||||
◇後半:午後3時00分〜午後4時30分 |
|||||||||
| 高エネルギーガンマ線で見る宇宙 | |||||||||
 |
物理学科 教授 林嘉夫(定員100名、講義) 現在,宇宙の観測は普通の光(可視光)のみならずいろいろな波長の光(電磁波)や荷電粒子,ニュートリノ,重力波などを使って行われています。宇宙は「見る」手段によって見え方が大きく異なります。中でもガンマ線は特に宇宙の活動の激しい部分を見ること ができます。宇宙の活動の激しいものとしては銀河中心や超新星爆発の残骸などがあげられます。ここでは,高エネルギーガンマ線を使った最新の観測方法,観測結果について解説します。
|
||||||||
| やさしい化学結合論 | |||||||||
 |
化学科 教授 岡田惠次(定員100名、講義) 化学は暗記の学問だと思ってはいませんか?確かにそういう面もあります。それは、皆さんが、新しい仲間と大学生活を始める状態と似ていると思います。まず友人の名前を覚え、性質を知ることから始めます。その後、いろんな楽しい連携プレーを考え出すことができます。化学もそれと同じです。ここでは、周期表からスタートして、原子の性質を知り、分子を組み立てます。簡単なルールを導入して、聞いたことの無い分子を、結合を表す線を使って書いてみましょう。分子を正しく描く事ができればその分子の性質や形をある程度予想する事ができます。高校で学ぶ範囲の初歩の化学を、ちょっと違った観点から扱います。化学が苦手な人、歓迎。
|
||||||||
| 大災害時代を生き抜く「水都大阪」の視点 | |||||||||
 |
地球学科 准教授 原口強(定員100名、講義) 水都大阪は、難波津の時代から近代に至るまで水運を活用しその恩恵を受け発展してきた。そこには恵まれた立地条件と絶え間ない人の英知があった。それは難波堀江開削以降、大和川、淀川などの自然を絶え間なく改変してきた歴史でもあった。その結果、「管理病棟、水都大阪」となった。今まさに確実にやってくる南海地震をはじめとする、迫り来る大災害時代を前に、「水都大阪」はこれを生き抜くことができるのか、について考察する。
|
||||||||