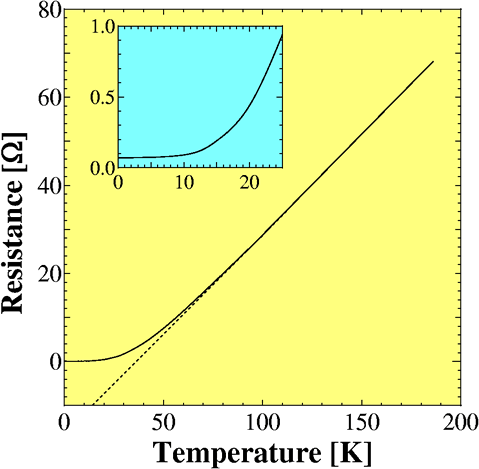
金属、とくに貴金属中を流れる電子は、熱振動している格子点の原子によって散乱される。温度が下がるに従い、散乱は弱くなるため、低温で電気抵抗は小さくなる。
ところが、十分低温では格子の熱運動は抑制され、最後に格子欠陥や不純物などによる散乱だけが生き残る。これらは温度によらない抵抗成分である。
従って、最終的には次のようなグラフを描くことになる。
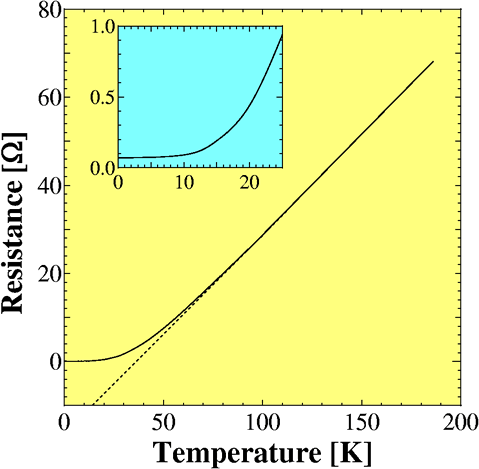
(グラフの中のグラフは低温部分の拡大図である。低温でも残留抵抗が生じている。)
現実的には、室温〜窒素温度よりもやや下の温度までの一次関数領域を利用することが多い。四端子法や四端子ブリッヂ法などを用いた通常の抵抗測定で比較的簡単に温度測定を行うことができる。ただし、通常の電気回路やさんで売っている「金属被膜抵抗」では温度変化が小さすぎて使い物にならない。
なお、皮膜・薄膜状にすることにより、不純物を導入せずに抵抗値をあげる事ができ、結果として高感度となる。巻き線状にすると抵抗値は稼げるが、インダクタンス成分が生ずるため、回路としての不具合が生ずることがある。
現実の半導体の電気伝導度は、二つの要因によって決まる。一つは金属の場合と同じ格子振動であって、もう一つは伝導を担うキャリアの濃度である。このうち、より金属的な半導体の場合、室温から窒素温度程度で格子振動の減少による伝導度の増大(抵抗値の減少)が見られる物があるが、実際には感度と再現性がないので温度計としては使わない。現実には格子振動の影響がなくなる低温で用いることになる。
さて、固体物理の初歩的な教科書には「真性半導体は絶対零度で絶縁体になる」という記述がある。その理由は、伝導を担う電子は100K程度のバンドギャップの上(伝導帯)に熱励起されている必要があるからであり、温度が下がるにつれて伝導帯上の電子は指数関数的に減少するからである、と書いてある。しかし、現実に使う半導体抵抗温度計は真性半導体ではなく、不純物半導体であり、低温においてはバンドギャップではなく、伝導体の直下にある不純物準位が意味を持つ。不純物準位と伝導帯の底の間のエネルギーは比較的小さい値なので、小さな温度変化で伝導帯への熱励起が可能となるのである。すなわち、不純物の導入の具合によって、半導体抵抗温度計の温度特性は大きく変わる。
現実には、ゲルマニウム、炭素、シリコン(PN接合ダイオード)やRuO2などの酸化物半導体を用いる。膜状あるいは棒状のものを樹脂で固めたものを加工して用いることが多い。市販のラジオ用炭素(体)抵抗器の中にも、低温における温度計として使える物がいくつかある。
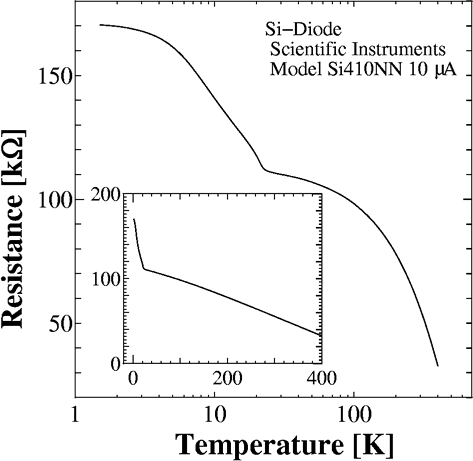
PN接合ダイオード(挿入図は線形軸で書き直したもの)。
低温で急激な立ち上がりを示している。
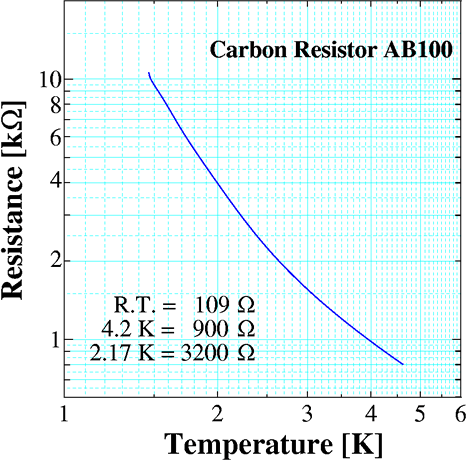
炭素体抵抗。低温で発散的に抵抗が増加する。プラスチック容器の中に、炭素の棒が入っており、その両端に金属の電極が接続されている。通常の炭素抵抗は絶縁体セラミックス柱の上に螺旋状の炭素膜が乗っているため、高周波ノイズに弱い。